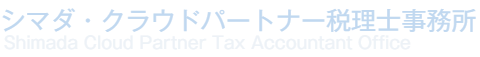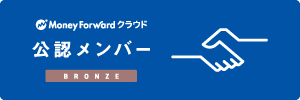早いもので今年も年末調整の季節が近づいてきましたね。
先日保険会社から生命保険料控除証明書の電子データ発行のお知らせメールが届き、もうそんな時期かと実感いたしました。
年末調整と言えば会社から配布される書類に手書きで記入して、保険会社などから送られてくる紙の証明書を付けて総務部・人事部・経理部などの担当者に提出するのが一般的だと思います。
実は一昨年(2020年)からこれら一連の流れが電子化可能なのをご存知でしたか?
今回は年末調整の電子化についてご紹介します。
まずは自社が年末調整の電子化に対応しているか確認!
一昨年(2020年)から始まった年末調整の電子化ですが導入している会社はまだまだ少ないのが実情です。
ただ、私の顧問先でも電子化を導入する会社が昨年は増えてきましたよ。
ということでまずは皆様がお勤めの会社が年末調整の電子化に対応しているか確認してみましょう!
今年は年末調整の電子化が始まって3年目、さらに電子帳簿保存法の改正(直接的な影響はありませんが)もあったりして電子化の機運が高まっている中ですので導入する会社も増えるのではないでしょうか。
もし皆様がお勤めの会社が年末調整の電子化に対応していたら次のステップはこちら!
年末調整アプリをダウンロードしよう
GoogleやYahoo!などの検索エンジン、App Store や Google Play(Playストア)などのアプリストアで「年末調整 国税庁」と検索してみてください。
そこから年末調整アプリをダウンロードして作成した書類はデータのまま又は印刷してご提出いただけます。
ただ、まだ令和4年分のアプリがリリースされていないようなのでまずは令和3年分のアプリで操作性を確かめてみて、令和4年分のアプリがリリースされたら本番の入力をしましょう。
生命保険料控除証明書などの証明書もデータ取込が可能ですが取り込めなかった場合は金額をアプリにご入力いただき証明書原本はそのままご提出ください。
なお、スマホからApp Store や Google Play(Playストア)などのアプリストアで年末調整ソフトを探すのは簡単でしたがPCからGoogleやYahoo!などの検索エンジンで「年末調整 国税庁」と検索しても国税庁のページが分かりづらいです。
Windowsをご使用の方はPC画面下の虫眼鏡マーク「ここに入力して検索」で「Microsoft Store」と入力してまずはMicrosoft Storeのアプリを立ち上げてください。
そして検索バーから「年末調整 国税庁」と検索すれば年末調整アプリが見つけられるはずです!
年末調整アプリで年末調整書類の作成!
年末調整アプリ自体は比較的わかりやすいUIになっていると思います。
私自身が税理士で年末調整に慣れているからかもしれませんが。。
ただ確実に言えるのは書面の扶養控除等申告書などを裏面の細かい説明書きを読みながら手書きで記入するよりは楽ということです!
書面の場合はどの申告書を書くべきか、さらに申告書のどこに何を書くべきか迷うことが多いですよね。
アプリの方は画面の質問に沿って進めていけば迷うことは無いと思いますよ。
ただ、アプリ特有の注意点がありますのでアプリを使う場合のポイントを以下にまとめますね。
IDはどのようなものにすればよいか事前に確認
社内の担当者が自社の給与計算ソフトに取り込む際のIDと年末調整アプリのIDは合わせる必要があります。
なので事前に社内の担当者にIDはどのようなものにすればよいか確認しておきましょう。
一般的には給与明細書などに記載されている社員コードを使うことが多いと思います。
パスワードは人に教えてもいいパスワードで
社内の担当者が給与計算ソフトに取り込む際にパスワードを入力することになります。
つまり社内の担当者にパスワードを教えることになりますので人に教えてもいいパスワードを使用する(他で使っている重要なパスワードは避ける)ようにしましょうね。
事前に社内でパスワードが設定される可能性もありますのでIDと一緒にパスワードもどのようなものにすればいいか確認する方がいいかもしれませんね。
なお、電子署名方式を利用すればID・パスワードは不要になりますがID・パスワード方式の方が簡単だと思います。
データで送ることが出来なかった場合は印刷して提出してもOK
データで送る場合、パソコンであればZIPファイルが作成されますのでそれをメールなりでお送りいただければOKです。
スマホの場合はメールアプリが起動されそこにZIPファイルが自動で添付されますのでそのままメールで送信できます。
ただ、私の顧問先で昨年、一昨年の状況を見ますと人によってはデータで送るのが難しかった人もいらっしゃいました。
パソコンやスマホの操作が苦手な人がそのようになっていた印象です。
そのような方でも紙に印刷するところまでたどり着ければ印刷したものを提出すればOKですよ。
社内の年末調整計算担当者はデータで提出してくれた方が入力の手間が省略出来て嬉しいのですが提出する側の従業員からすればデータ提出でも印刷した紙提出でもそれほど手間は変わらないですね。
証明書の電子取込は難易度が高い?
年末調整電子化の最終形(完全版)は証明書の電子取込です。
私の顧問先で昨年の状況を見ますとここまでたどり着けた人はゼロでした。
実は私も電子化初年度の一昨年は取り込みできずでしたが、昨年ようやく取り込みに成功しました。
皆さんもぜひ挑戦してみてください。
しかし、いくつかハードルがあります。
まずはご自身でマイナンバーカードを発行している必要があります。
そしてマイナポータルの利用を開始します。
さらに証明書の発行元である生命保険会社などでマイナポータルとの連携サービスに申し込みます。
連携がうまくいくとマイナポータル内のe-私書箱に証明書の電子データが届くことになります。
ここまで出来ればあとは証明書データをダウンロードして年末調整アプリに取り込むだけです。
実は証明書の電子交付に対応している会社が少ない
そうなんです、実は証明書の電子交付に対応している会社が少ないんです。
生命保険会社は大手各社対応が完了している印象です。
住宅ローン控除は住宅金融支援機構のみ対応で銀行は全て未対応です。
まあ、住宅ローン控除は令和5年分以降そもそも添付が不要になる方向ですので電子交付には対応しない感じですかね。
証券会社やふるさと納税関係は年末調整とは関係ありませんが確定申告で電子データ取り込みができますので併せてご確認、ご検討頂ければと思います。
現在の利用可能企業一覧はこちらをご確認ください。
https://e-shishobako.ne.jp/bulk/kigyo_ichiran
まとめ
ここ数年の税制改正で年末調整時に会社に提出する書類の数が増えましたよね。
さらに1枚に記載する内容も増えて複雑化してきています。
例年、顧問先以外でも家族や友人から「どう書いたらいいか分からないから教えてほしい」という連絡をたくさんもらいます。
複雑化もありますがそもそも今って紙の書類に手書きすることが減りましたので紙に手書きすることが億劫になってますよね。
年末調整書類にお困りの皆さん、今年はアプリでの作成にチャレンジしてみてください!