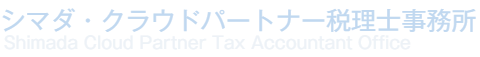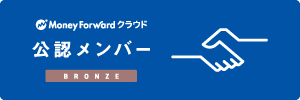法人は事業活動を行っている場合、赤字であっても発生する税金があります。
それが法人住民税の均等割です。
資本金1億円超の法人の法人事業税外形標準課税も赤字法人に発生しますが今回は省略で。
法人住民税均等割とは
地方税法第23条(道府県民税に関する用語の意義)によると
均等割 → 均等の額によつて課する道府県民税をいう。
とのことです。うん。そのままですね。
法人はその他に法人税の額を課税標準とする法人税割がありますね。
法人住民税均等割の課税標準は
地方税法第52条 (法人の均等割の税率)によると
法人の均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める額とする。
とのことです。
詳細は省略しますが簡単に言うと法人の区分(普通法人とか公益法人とか)、期末資本金等の額、期末従業者数に応じて金額が決まります。(以下、東京都の均等割の表です)

中小零細企業の多くは資本金等の額も従業者数も一番低い区分に入り年間7万円になりますね。
法人住民税均等割の負担を軽減しよう
今回とある法人で検討した事例です。
資本金等の額を下げる検討をしました。
現状は資本金3千万円です。
別表五(一)を見てみましょう。

この状態だと資本金等の額が3千万円なので従業者数が50人以下として均等割は18万円ですね。
次に均等割の負担軽減対策です。
まずは自己株式を2千万円分取得します。
別表五(一)を見てみましょう。

ここでの注意はみなし配当が生じないように取得株数を設定することですね。
今回の例では資本金等の額3千万円÷発行済み株式数300株=100,000円が1株当たりの購入金額。
2千万円÷100,000円=200株が取得株式数ですね。
200株を超えるとみなし配当が生じます。
これで法人税法上の資本金等の額は1千万円になりましたので均等割が7万円になると思いますよね。
平成27年3月31日まではそうでした。
平成27年4月1日以後(開始事業年度)からはそうはいかなくなりました。
「資本金+資本準備金」が法人税法上の資本金等の額を上回っていると均等割の判定に「資本金+資本準備金」を使うことになってしまったためです。
そのためもうひと手間必要です。
何をやるかというと、無償減資です。
資本金を減らして「その他資本剰余金」に振り替えます。

これで「資本金+資本準備金」も法人税法上の資本金等の額も1千万円になり無事均等割が7万円になります。
別の方法として「有償減資」や「無償減資+欠損填補」という方法もあります。
「有償減資」だと支払った金額を利益積立金額と資本金等の額の比で案分してそれぞれを減らすので儲かっている会社で利益剰余金(利益積立金額)が多くある場合はかなり大きい金額を支払わなければなりません。
さらに利益積立金額の支払いとされる部分はみなし配当になり配当可能限度額にも注意が必要になります。
「無償減資+欠損填補」だと利益剰余金(利益積立金額)がマイナスであることが前提なので儲かっている会社で利益剰余金(利益積立金額)がプラスの場合は使えないですね。
ご参考になれば幸いです。