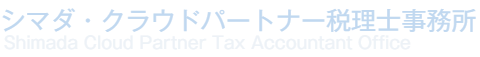ここ最近、上場企業などの大き目な企業を中心に源泉所得税の税務調査が入るケースが増えているように感じます。
しかも国際的な案件に対するものに的を絞っているという印象です。
海外送金とか海外出張者に対する給与とか。
今回はとある上場企業の源泉所得税の調査で着目された外国人技能実習生に支給する給与に係る所得税の源泉徴収についてです。
外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度は、もともと1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が好評となり、同様の手法を日本国内で実施するため1993年に制度化されたもののようです。
制度化の目的・趣旨は、日本の技能、技術又は知識を開発途上地域等へ伝え、開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の一環のようです。
ただ、現実的には安価な労働力の確保のために利用されているケースもあるようですね。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本で企業と雇用関係を結び、出身国で修得が困難な技能等の修得を図るものです。
期間は最長5年で、技能等の修得は技能実習計画に基づいて行われます。
給与に対する源泉所得税
さっそく本題ですが、技能実習生は企業と雇用関係を結びますので当然給与が出ます。
給与に対する所得税の源泉徴収は居住者であれば扶養控除等申告書の提出の有無に応じて源泉徴収税額表の甲欄、乙欄に当てはめて源泉徴収税額を算出しますよね。
非居住者であれば一律20.42%の税率で源泉徴収することになります。
ここが一つ目のポイントですね。
居住者か非居住者か
所得税法上、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいいます。
「非居住者」は「居住者」以外の個人と規定されていますので日本に「住所」がなく1年以上「居所」が無い場合「非居住者」になります。
「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになるとされていますが外国人技能実習生の場合は「生活の本拠」は本国にあると思われますので日本に1年以上「居所」があるか否かがポイントになると思われます。
外国人技能実習生の場合、給与は決して高くありませんから非居住者で20.42%の源泉徴収になるより居住者で源泉徴収税額表の甲欄に当てはめる方が源泉徴収税額は安くなりますね。
しかし次のポイントも重要になります。
租税条約があるか否か
非居住者に該当した場合、次にチェックするポイントが日本と外国人技能実習生の本国との間で租税条約が締結されているか、締結されている場合、事業修習者に対する免税の条項があるか、です。
事業修習者に対する免税の条項があれば源泉徴収不要になります。
ちなみに事業修習者と似ている言葉で事業習得者という言葉がありますが両者の一般的な意義は以下の通りです。
事業修習者……企業内の見習研修者や日本の職業訓練所等において訓練、研修を受ける者
事業習得者……企業の使用人として又は契約に基づき、当該企業以外の者から高度な職業上の経験等を習得する者
外国人技能実習生は事業修習者に該当するものと整理されているようです。
租税条約に事業修習者に対する免税の条項があった場合、次に注意する点があります。
外国人技能実習生の勤務実態
結局ここが税務調査等で問題になります。
税務署側は少しでも多く税金を徴収したいのでまずは日本にいた期間が1年未満の外国人技能実習生をピックアップします。
ピックアップした外国人技能実習生に対して20.42%で源泉徴収していない場合、指摘されるというわけです。
ここでこちら側の切り返しとして租税条約の存在を提示します。
本当は事前に租税条約に関する届出書を提出しておかないといけないんですが実務上は後出しも認められます。(加算税等のペナルティは徴収されるので注意ですが)
租税条約に関する届出書を提出する場合に次に確認されるのが外国人技能実習生の勤務実態です。
勤務実態が租税条約に規定されている事業修習者に該当しないとされると租税条約が適用できないので20.42%の源泉徴収が必要になってしまうというわけです。
ポイントは外国人技能実習制度で認定された技能実習計画に沿った勤務実態であるか否かです。
業務内容も重要ですが、残業をさせていないことも重要です。
技能実習計画には残業の考え方はないでしょうから残業をさせていると企業内の見習研修という範囲を逸脱していると取られかねません。
「平21.3.24、裁決事例」でこのあたりが争われておりますのでご参考になさってください。
まとめ
国際的な源泉所得税の税務調査では租税条約の適用の有無が重要なポイントになります。
調査官に指摘されたらまずは指摘内容をしかっり確認し、適用できる租税条約が無いかじっくり検討しましょう。